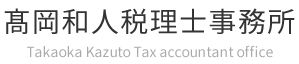事業承継・M&A補助金とは?引継ぎ補助金との違いや要件など
会社の事業を後継者に承継したいと考えた場合に活用できる補助金として、事業承継・M&A補助金があります。
今回は事業承継・M&A補助金とは何か、前身の引継ぎ補助金との違いなどについて紹介します。
事業承継・M&A補助金とは?
事業承継・M&A補助金とは、中小企業や小規模事業者が、事業承継やM&Aを行う際に、その費用の一部を国が補助する制度です。
この補助金は、後継者不足や経営者の高齢化といった社会問題を背景に、事業の継続を支援することを目的としています。
補助金の対象となる経費は、M&Aの仲介手数料や、専門家への相談費用、登記費用など、多岐にわたります。
補助金は、事業承継の形態に応じて、複数の枠に分かれています。
補助金を利用することで、事業承継にかかる経済的な負担を軽減し、円滑な事業承継を促すことができます。
この制度は、事業承継の準備から実行、その後の経営統合まで、幅広く支援します。
事業承継は、会社の永続的な発展のために不可欠であり、この補助金は、そのプロセスをスムーズに進めるための強力な後押しとなります。
事業承継促進枠
事業承継促進枠は、主に事業承継を行う際の経費を補助するための枠です。
後継者が事業を引き継ぐために必要な専門家への相談費用や、登記費用などが補助の対象となります。
この枠は、事業承継を検討している中小企業や小規模事業者を支援し、円滑な事業承継を促すことを目的としています。
後継者が、M&Aによって事業を引き継ぐ場合も、この枠を利用できます。
補助金の額は、事業の規模や内容によって異なりますが、数十万円から数百万円まで補助される場合があります。
ただし賃上げなどを行う場合には補助金の上限額が、1000万円に引き上げられる可能性があります。
この補助金を活用すれば、後継者が事業を引き継ぐ際の経済的な負担を大幅に軽減できます。
専門家活用枠
専門家活用枠は、事業承継やM&Aを円滑に進めるために、弁護士、税理士、M&A仲介業者などの専門家に支払う費用を補助するための枠です。
M&Aの仲介手数料や、デューデリジェンス(企業価値の調査)費用、法務や税務に関する相談費用などが補助の対象となります。
M&Aは、専門的な知識が必要なため、専門家のサポートが不可欠である一方、専門家への費用は高額になることが多いです。
専門家活用枠を活用すれば、経済的な負担を軽減できます。
補助金の額は、依頼する専門家の種類や、依頼内容によって異なりますが、基本的には600万円から800万円までといわれています。
PMI推進枠
PMI推進枠は、M&Aが完了した後に、経営統合を円滑に進めるための経費を補助する枠です。
PMIとは、「ポスト・マージャー・インテグレーション」の略で、M&A後の組織や業務、システムなどの統合を指します。
PMIが円滑に進まなければ、M&Aの目的を達成することは困難です。
この枠は、M&A後の新たな事業計画の策定や、従業員への研修、新しいシステムの導入など、経営統合にかかる費用を補助します。
補助金の額は、M&Aの規模や、経営統合にかかる費用によって異なりますが、最大で数百万円まで補助される場合があります。
この枠を活用すれば、M&A後の会社の成長を加速させることが可能となります。
廃業・チャレンジ枠
廃業・チャレンジ枠は、後継者がいないため廃業を検討している中小企業や小規模事業者を支援するための枠です。
廃業にかかる費用を補助することで、円滑な廃業を促します。
また、廃業後に、新しい事業にチャレンジする費用も補助の対象となります。
たとえば、新しい事業の立ち上げにかかる費用や、専門家への相談費用などが補助の対象となります。
この枠は、事業承継やM&Aが難しい事業者が、スムーズな廃業と再チャレンジができるように支援することを目的としています。
前身の事業承継・引継ぎ補助金との違いは?
事業承継・M&A補助金は、2025年度から始まる新しい制度ですが、その前身には「事業承継・引継ぎ補助金」がありました。
両者の大きな違いは、補助金の対象範囲です。
事業承継・引継ぎ補助金には「経営革新枠」などがあり、事業承継・M&A補助金ではこれを「事業承継促進枠」に名称を変更しました。
また、事業承継・引継ぎ補助金では「廃業・再チャレンジ枠」が補助対象でしたが、事業承継・M&A補助金は、それに加えてM&A後の経営統合を支援する「PMI推進枠」が新たに設けられました。
また、補助金の上限も事業承継・引継ぎ補助金よりも全体的に高くなっている点も違いといえます。
この変更点は、国が企業の持続的な成長を推進したいという方針が反映されているかたちであると考えられます。
まとめ
今回は事業承継・M&A補助金の概要について紹介しました。
補助金を利用することで、事業承継やM&Aが円滑に進みやすくなります。
とはいえ、活用する場合の準備は非常に複雑なため、利用を検討している方は税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
タンス預金は相続税対...
現在、日本の個人の金融資産総額は約2000兆円といわれており、現預金が約半数を占[...]

-
農業簿記とは
農業経営は、一般的な業種に比べて、保有する資産の種類も多く、生産される作物の種類[...]

-
会社を合併するデメリ...
会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新[...]

-
合併手続の流れ
会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新[...]

-
資金繰り改善のための...
資金繰りのために資金調達を行うことを考えている経営者も多いかと思います。資金繰り[...]

-
小規模宅地等の特例と...
相続税の申告で、大きな負担となりやすいのが自宅や事業用の土地の評価額です。特に都[...]

よく検索されるキーワード
Search Keyword
-
- おいらせ町の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 北上市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 青森市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 五所川原市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 三戸郡 事業支援
- 三沢市 経営支援
- 三戸郡 経営支援
- 深浦町の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 十和田市 中小企業経営革新支援
- 平泉町の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 八幡平市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 花巻市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 普代村の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 雫石町の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 三戸郡 経営計画 管理会計
- 平川市の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 三沢市 資金繰り
- 田野畑村の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
- 三戸郡 記帳代行 経理代行
- 九戸郡の相続税 贈与税 事業承継 農業経理
資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
-
- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
-
- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
-
- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
-
- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
| 対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |